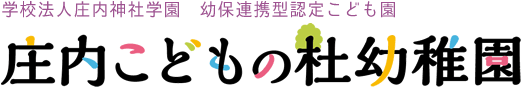園長つうしん
~庄内こどもの杜幼稚園の見えない秘密(お手伝い隊の意味)~
今回の見えない秘密は、「年長児のお手伝い隊の意味」についてです。
当園年長児の独特の活動として、「お手伝い隊」があります。
お手伝い隊は、たそがれコンサート、運動会、劇あそび会など、園の大きな行事で活動します。これは大人が用意した活動ではなく、行事をよりよくするために自分たちで何をするか企画し、ごっこ遊びではなく行事で行う本当の仕事として任され実践します。
限られた活動時間内ではありますが、活動する姿をみると、年長児ながら責任感をもって活動している姿が見かけられます。
3回の活動があることで、ホップ(知る)・ステップ(わかる)・ジャンプ(できる)と、継続した経験となります。
この自分たちで考えたお手伝い隊を活動する中で、自分たちのクラスだけでなく全園児や保護者のためにと視野を広げながら、協働性(友達と共通の目的に向かって工夫や協力すること)を発揮します。
今までの活動では、大まかに分類すると、全体的な広報をしてくれる活動、年下のお世話をしてくれる活動、道具や配置の業務を手伝ってくれる活動、当日までの準備物や景品を作成してくれる活動です。
この活動は、花形の選手や俳優を引き立たせてくれるため、あるいは当日の観客をもてなしてもらうためと、どれも社会では裏方と言われる主役ではない活動ばかりです(子どもは主役と思っているかもしれませんが)
誰かのために行動した結果、年下の子や保護者、先生から「ありがとう」と言われる喜びを感じながら達成感を味わいます。
こうした経験は、子どもたちの自己有用感(人の役に立てたという実感)を高め、自信へとつながっていきます。
また、お手伝い隊の姿を見たり、されたりしている年下の園児にとっては、あこがれの姿として覚えていて、次に自分たちが行う時期につながる体験となっています。
この活動が始まった景気は、大人が考えた活動ばかりするのではなく、主体性を発揮しながら、何をするかを自ら考え、自ら実践し、自ら振り返り、また自らやり直す。こんなトライ&エラーを、偽物ではない活動としてやり遂げる。
小学校に行ってからだけではなく、社会人としても必要な力を育むためのものです。
少子化の今、きょうだいや地域での縦関係や横関係も薄れてきました。またそれに追い打ちをかけるかのように、コロナ禍で人の関係性はより途切れてしまいました。
今地域社会は、人口減少や少子高齢化に伴い、活動が苦しくなっているところが増加しています。この社会を生きていく子どもたちにこのお手伝い隊を通じて、「みんなのなかで やりたいことをする人」として、社会を支える人材になって欲しいと願っています。
2025年11月1日