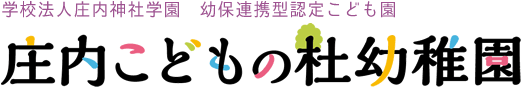園が目指す子ども像
「みんなのなかでやりたいことをする人」に
20年後の日本は、超少子高齢化、働き手減少、年金問題、8050問題、AI・ICT化、今ある仕事の半分はなくなるなど、他国より先に未経験の問題に遭遇すると言われています。
世界規模の問題で見れば、環境問題、貧困問題、人口増による食糧問題なども降りかかってきます。
「これをすれば大丈夫」と事前準備のできない、何が課題か分からない世の中。
あちらを立てればこちらが立たずの、「みんなが同意できる正解がない」世の中。そんな時代をより良く生きる為、子ども達は「みんなのなかで、やりたいことをする人」に育って欲しい。
「みんな」とは、社会です。
社会は家族からはじまって、幼稚園、小学校から大学、職場、地域社会、そして世界と、その人の時期やステージによって、様々なサイズの「みんなの社会」があります。
社会で独自性のある自己発揮をすることが、「やりたいことをする」ということです。
「やりたいことをする」には、「みんなの社会」を無視した自己中⼼的⾏為ではいけません。
それぞれの「みんな」の問題に対して、他人事ではなく、自分ごとにとらえることが出来てこそ「みんなのなかで、やりたいこと」ができます。
自らしたいことを自ら考え、自ら決め、自ら進めていく。そして、自ら振り返り、自ら再チャレンジする。
「やりたいこと」とは「やらなければならないこと」ではありません。「やらなければならないこと」は受動的ですから。
「やらなければならないこと」が「やりたいこと」という自分のミッションになって初めて、意欲的な活動になったと言えます。
他者から与えられた「やらなければならないこと」ではなく、「自分が本当にやりたいこと」を自己決定できるようになるには、意欲と、探求⼼と、協働性が求められます。
もちろん「みんなのなかで、やりたいことをする人」の⼟台は、「自分が愛されている」という自己肯定感や、「自分は意味ある存在だ」という自己有⽤感があってこそ。これがないと、意欲はわきません。
園は、そんな人間に育つきっかけとなるような保育でありたいのです。
子どもを取り巻く大人(職員・保護者等)は、子どもに育つきっかけをあたえられるような、意味ある人でありたいです。
自己中⼼的でもなく、受動的でもなく、成功や失敗にとらわれることなく、その時その瞬間の主人公となり、自分のやりたいことを伝えながらも、その場の人たちと協働できる。必要ならば、やりたいことをする場をつくれる。
それが、社会に出て、それぞれの場所で、自分なりに輝ける人材になれるように。