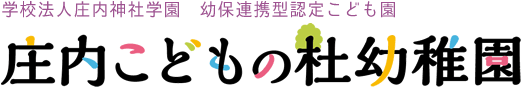園長つうしん
園長通信(令和7年9月号)
園長つぶやき~園関係者が「みんなのなかで、やりたいことをする人」に~
「ありがとうに気づくには」
40度に近づく気温が続き、屋外に出ることすら躊 躇する日々が続きますが、子どもたちは与えられた遊び場で楽しく過ごしています。
ただこの時期、室内遊びがあたりまえの日常に、子どもの発達に対する懸念を持ちます。
子どもの外遊びのように、今まで当たり前にあったものがなくなった時に、人はその事象の重さや大切さに気づきます。
でも、有ることや無いことが日常である人たちが、この当たり前に有るものや無いものの価値に気づくことはとても難しいものです。
8月は、広島や長崎の原子爆弾が投下された日や終戦記念日があり、平和を再確認させられる式典をよく目にします。
今でも報道されるウクライナやイスラエルのガザ地区等の紛争の様子を見ると、いかに日本が平和であるかということに気づかされます。
我々日本人が当たり前に思っている平和のありがたさを自ら感じとることは難しく、単に教科書的な伝達では理解することはできません。
しかしこの平和を伝えてもらうには、原爆の被爆者や戦争体験者の方々のように魂をもって伝えてくれる人達が不可欠なのですが、現在この方々が高齢のため語る活動が岐路に立っています。
「ありがとう」は、漢字で記載すると「有難う=有ることが難しい」と記載します。
自らが不自由なく生活して、現状が満たされた現代では、様々な事象に対して「ありがとう」と改めて自覚するのは、平和を理解すると同様にとても難しい状況になっています。
満たされすぎることで、「有ること難しい」と感じる機会がないのです。
当園の保育でも、この「有難い」に気づいてもらうため、不足・不便・不潔・不満など、たくさんの「不」を意図的に体験させています。
家庭や地域にはない「有ることが難しい」ことを体験することこそが、当たり前ではなかったと気づく経験だからです。
今Z世代と言われる子どもたちが、被災者に代わって平和の語り部を引き継いでいるそうです。この子たちに負けず、「有難い」経験を知れる、園でありたいと思います。
2025年9月1日