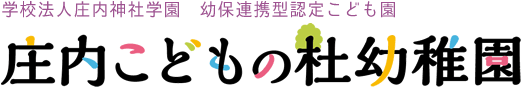園長つうしん
園長通信(令和7年8月号)
園長つぶやき~園関係者が「みんなのなかで、やりたいことをする人」に~
「人間関係の距離を調整する」
例年よりもはやい梅雨明けのため、猛暑が続く7月でしたが、子どもたちは変わらぬ姿で日々の生活を謳歌しています。
先月の参議院選挙では、どの候補者も選挙活動におけるSNSの活用がより重要性を増したと言うように、ネット社会は切っても切り離せないものとなっています。
そんな社会を横目に、1号保育がある日は、できるだけ毎日正門に立たせてもらい、登園する園児・保護者だけでなく、地域の方にも挨拶をしていますが、時折こちらの挨拶を気づかぬかのようにずっとスマートフォンに目をやる人がおられます。
最近ですが、人間の距離感について変わってきたのではないかと思うことがあります。
その傾向は、コロナ禍でより顕著となり、促進されたように見受けられます。
変わったと思う人の距離感とは、「距離感が離れていった」という点です。
コロナ禍ではソーシャルディスタンスという言葉が使われるようになりました。
この言葉はアメリカの人類学博士、エドワード・ホールが提唱した概念で、相手に対して抱いている感情と距離との関係を明らかにしたものです。
ソーシャルディスタンスとは「社会距離」のことで、例えば知人と呼べる関係の人と話し合う距離感で約122~366 ㎝と言われています。
一方パーソナルディスタンス「個体距離」という言葉もあり、これは例えば友人や家族と話すときに取る距離感で約6〜122cmとされています。
社会距離・個体距離は、話し合うのに心地よい、関係性の近い遠いで距離が変わります。
近年はこのヒトの距離感がどんどん遠くなってきていて、場合によっては接続すること自体望まないことも出てきています。
しかし望むも望まぬとも、友人や家族のように感じられない上司や同僚と近い距離で話をし、仕事や生活を共にしていかなければならないのが現実です。
いくらITやAIが発展しても、まったく人と接することがなく生活をすることはありえず、人間関係の距離を詰めることができない人が、社会での適応に苦労しています。
この人間関係の距離を調整する学び初めは、他者の存在を意識できる幼児期からです。
ごちゃごちゃしたアナログ幼稚園生活で、他者の存在の中で調整する学びがなされます。
この幼児期の学びは、今の時代とても貴重な学びといえるのではないでしょうか。
2025年8月1日