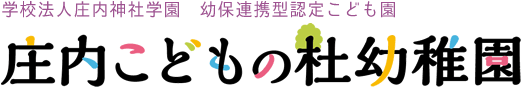TOPICS
園長通信(令和6年8月号)
園長つぶやき~園関係者が「みんなのなかで、やりたいことをする人」に~
梅雨も終わり、いよいよ本格的に猛暑の夏がやってきました。
今は夏休み期間、長時間利用園児達はプール遊びを中心に日々過ごしています。
さて最近、出版販売額が減少し続けている統計に表れてるように、本や雑誌を目にすることが減り、説明書のような文語体を触れる機会が少なくなっています。
文語体の言葉を触れることが減っている一方で、喋り言葉の口語体に触れる機会は、SNSやネット社会がいつも側にある現在ではとても増えています。
文語体は単に「書いている文字」、口語体は「しゃべり言葉」のことでではなく、以下の特徴を持つものです。
・口語体の特徴は「短文、散文、話コトバ、感情的、思い付き、ラフ」
・文語体の特徴は「中長文、定型文、論理コトバ、論理構造、推敲、形式」
文語体文化から口語体文化への変化は、時代の流れとして仕方がないと思いますが、その変化で失われているのがコミュニケーション能力だと思っています。
コミュニケーション能力の2つの要素は「きく」と「はなす」です。
世の中に散見するミスコミュニケーションの原因の多くは、この「きく」と「はなす」の「省略、歪曲、一般化、環境」が要因とされています。
【はなす】
省略:自分が持っている全ての情報、必要な情報を相手に言葉にして伝えていない
(曖昧、言葉足らず、具体情報不足(いつ・誰が、暗黙の習慣を非伝達)。
歪曲:事実をありのままではなく、自分の解釈を加え等)情報を言葉にして伝えている(偏見、一方的)。
一般化:一部の情報を、あたかも全体の情報であるかのように、決めつけて伝えている
(みんなが、どこでも、いつも)。
感情:雑な言い方、極度の緊張、怒らせないよう相手の感情や反応ばかり気にする。
感情的に威圧、怒鳴る。
【きく】
省略:相手の情報の本質を理解していない。曖昧に聞く。もしくは聞いていない。
歪曲:事実をありのままではなく、自分の解釈を加えた情報にして聞く(誤解)
一般化:一部の情報を、あたかも全体の情報であるかのように、決めつけ聞く
感情:粗雑な聞き方、不明点があっても、聞きにくい相手で質問できない。内容による過激な反応、落ち着ず急進的なリアクション。
口語体文化が進むと、どうしても上記の四要因を引き起こしやすくなります。
ミスコミュニケーション事案を多く見かける今、自分の「はなす」「きく」言葉を今一度振り返ってみてはどうでしょうか?
2024年8月1日